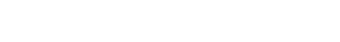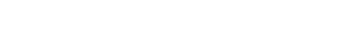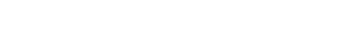医療業界における高齢者需要の伸び
「ときどき入院、ほぼ在宅」の言葉が象徴するように、在宅での療養生活の整備がますます求められています。地域包括ケアシステムの整備のために、2年後の診療報酬と介護報酬のダブル改定を控え、医療機関でも介護事業との関わりを考えていかなければならない時期と言えます。
本号から「院長のための介護保険の基礎知識」と題して、4回シリーズで医療機関から見た介護保険事業のポイントについて考えていきます。第1回では、診療報酬と介護報酬の動向と制度の違いを整理します。
診療報酬の動向
言うまでもなく地域包括ケアシステムが共通のキーワードです。
入院機能においては、在宅復帰を推奨するとともに、受け皿としての在宅医療は、主治医機能の強化として重度対応や看取り、認知症への対応の強化が求められています。
また、在宅での療養生活を支えるため、維持期のリハビリテーションの診療報酬から介護報酬への移行がますます進められています。
介護報酬の動向
中重度の要介護者支援の強化とリハビリテーションの推進や看取り対応の充実は診療報酬改定に先立って同様の方向で進められています。デイサービスでは、看護職員の機能の効率化から病院や診療所、訪問看護ステーションからの看護職員の配置が認められるとともに、居宅介護支援事業所では、特定事業所集中減算が全サービス対象となるなど、機能の効率化とともに囲い込みへの牽制機能が強化されています。
医療と介護事業の制度上の違い
さて、一見同様の方向を向いているように見える医療と介護事業ですが、その制度には大きな違いがあります。
①契約書・重要事項説明書の取り交し
医療機関で介護事業を進めるとき、たとえば、訪問診療を居宅療養管理指導で算定する場合などを含めて、介護事業は全て重要事項説明書と契約書を取り交わすことが必要となります。契約書や重要事項説明書は行政指導の重点項目となっています。
②ケアマネジャーとの協力体制
介護事業は、医師が中心ではなくケアマネジャーを中心としたしくみです。原則としてケアマネジャーの作成するケアプランに基づきサービス提供が行われます。そのため通所リハビリテーションなど医療系の介護事業には、指示書が必要となります。居宅療養管理指導の場合でも、ケアマネジャーに情報提供をしなければ算定できないこととなっています。医療や介護の知識や用語が混在する中、ケアマネジャーとの間で情報共有を図ることは難しいと言う医師の話をよく聞きますが、ケアマネジャーとの協力体制がとれなければ、介護事業を増やすことは難しいでしょう。利用者の状態をわかりやすい言葉で伝えるなど、ケアマネジャーをサポートすることも医療機関には求められます。
③要介護度別の区分支給限度基準額
在宅で介護保険を利用する場合、要介護度別に限度額(区分支給限度基準額)が決められています。この上限を超えても利用することは可能ですが、利用者の自己負担が異なってきます。限度額内なら1割(もしくは2割)の負担で済みますが、限度額を超えた分のみ10割負担となります。つまり、たとえば500単位超えた場合、1割で約500円のはずが約5,000円の負担になります。ケアマネジャーは利用者に代わって限度額を管理しているため、上限を超えた場合、料金を負担する利用者とサービスを提供する事業所との板挟みに陥ります。サービスを提供している利用者ごとに限度を超えた場合の対応について、ケアマネジャーに確認しておくと良いでしょう。
各自治体では、事業者に対し、毎年集団指導を行っています。今回ご紹介した内容以外にも介護事業を行う上での留意点などの説明がありますので内容をよく把握しておく必要があります。